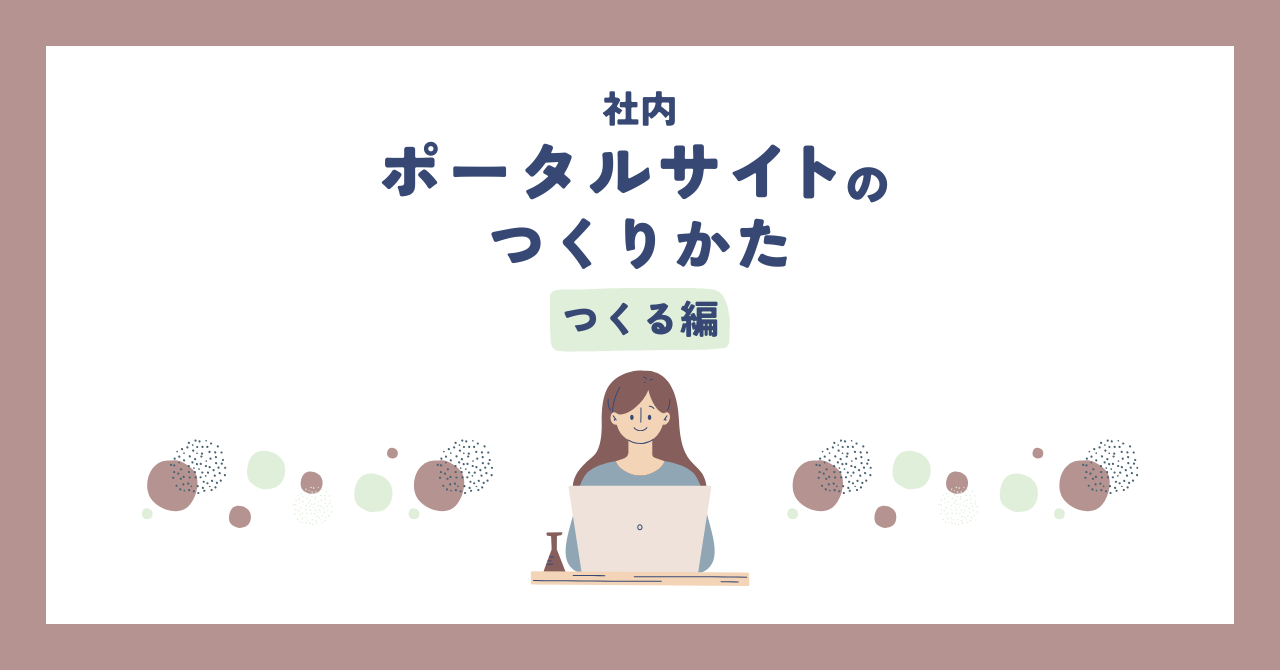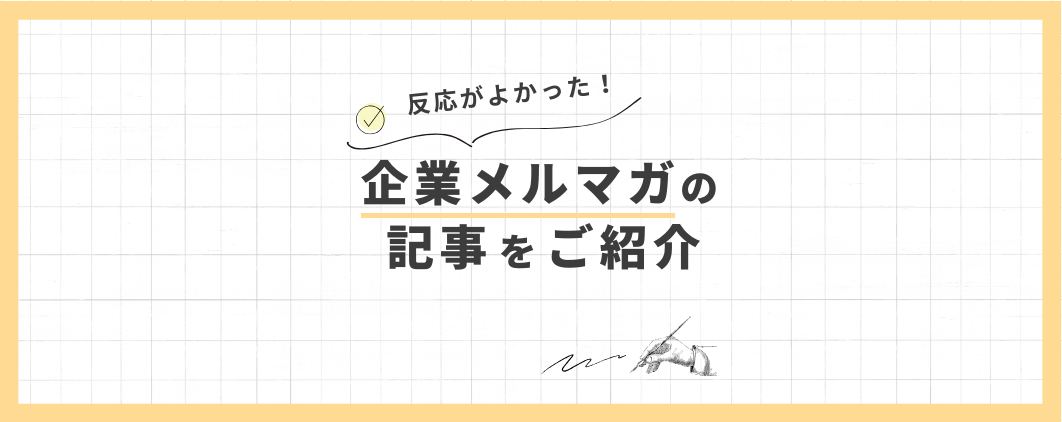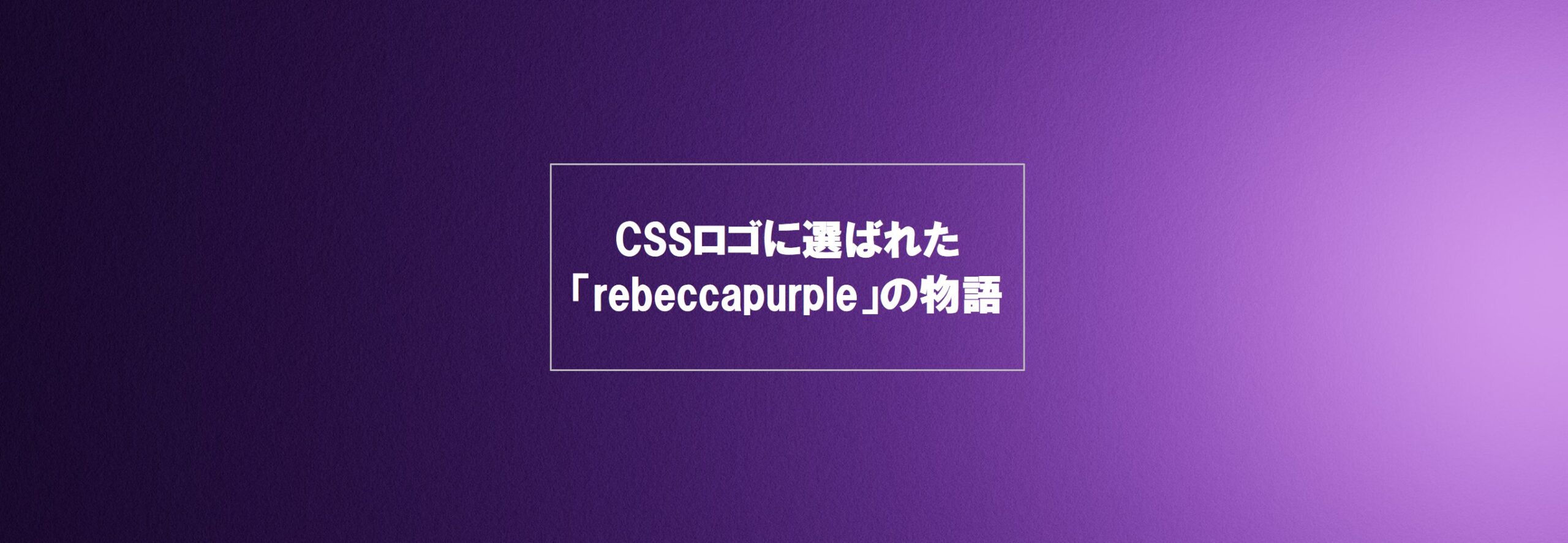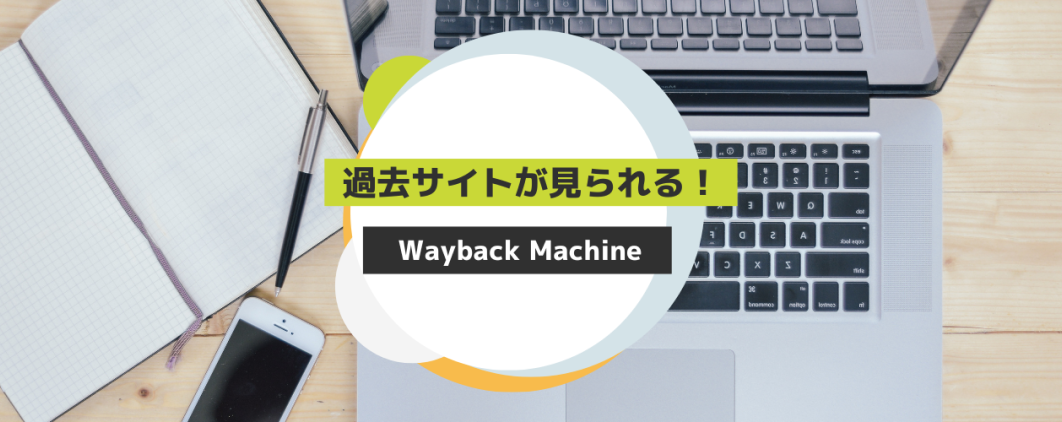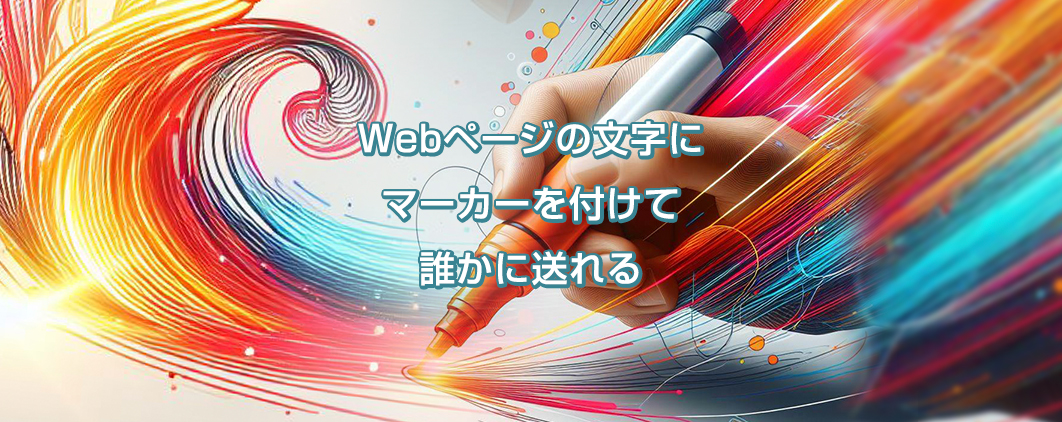こんにちは。デザイナーの山中です。
最近すっかり朝晩は冷えて布団から出るのが困難な季節になってきましたね。
あと10分だけ……を繰り返す毎日です。
さて、そんな私はソフトコムでは主にバナー制作を担当しています。
2児の母として時短勤務で働き、今年で3年目に突入しました。
デザイン制作にチェック、修正対応、迫る納期にお迎えの時間……1日があっという間の中で、日々「時間」との付き合い方を模索しています。
短い勤務時間の中でクオリティを保ちつつ、お客様の期待を超えるデザインをどう生み出すか……。
そんな中で私が頼りにしているのが、AIを活用した「考える時間」のサポートです。
PhotoshopやChatGPTなどのAI機能をうまく取り入れることで、作業効率を上げながら、より深い表現を目指せるようになりました。
しかしながら、生成AIによる画像やテキストは著作権の扱いに注意が必要なため、社内では素材の一部補正や参考用として限定的に活用しています。
AIに頼りすぎず、上手に使うことで、最終的な品質と安全性を両立したいと考えています。
ここからは、普段はどのようにAIを使用しているかご紹介します。
今まさに時間に追われていて働き方を見直したい方や、生成AIに興味はあるけど著作権とか危ないんじゃないの?と不安に思っていらっしゃる方の参考になれば嬉しいです!
PhotoshopのAI機能で作業時間を短縮!
制作の現場では、不要部分の除去や背景処理や微調整など、細かな作業に意外と時間がかかります。
以前は商材と共に写る背景に近しい素材をシャッターストック等で探して商材を切り抜いて合成したり、コピースタンプツールを使ったり…と手間も時間もかかっていたのですが、最近は壁を引き延ばしたり、撮影時に移りこんだ汚れの除去などの簡単な合成作業はPhotoshopの「コンテンツに応じた塗りつぶし機能」を使ってスピーディに行うことが増えました。
下記の方法で生成塗りつぶしが出来るので、ぜひお試しください!
- 塗りつぶしたい場所を選択ツールで囲う
- メニューバーの「編集」→「コンテンツに応じた塗りつぶし」→「OK」
ChatGPTは“発想の相棒”に
もうひとつの心強い味方がChatGPTです。
依頼内容によってはバナー制作の際に商材を魅力的に見せるテキスト(キャッチコピー)が必要になります。
お客様から「この言葉を使ってね」と単語や簡単な言葉のみで制作をする場合も。
いただいたお仕事には真摯に取り組みますが、しかしながら私は言葉のプロではありません。
その際に、ChatGPTに相談をします。
私は主にChatGPTに相談する際にはターゲット層や商材の特徴の他に「〇〇文字以内」や「〇案欲しい」と数の制限をしてコピーを生成しています。
キャッチコピーや構成案を考える際に、「この商材(または企画)の魅力をもっと端的に伝えるにはどのようなコピーが最適か?」と相談すると、複数の角度から提案をくれます。
また、「このコピーってどういう層に伝わるかな?」と私が考えたコピーをChatGPTに客観的に判断をしてもらうことも。
お客様からご提案されたコピーが長くてバナー内に収めきることが難しい時にもChatGPTに「〇〇文字以内にリライトしてほしい」と相談することもあります。
もちろん、AIの案をそのまま使うのではありません。AIの案を元に再度自分の言葉に落とし込みます。
AIを発想のヒントや視点の拡張として活用することで、結果的に提案スピードと完成度の両方が向上しました。
“人にしかできない部分”に時間を使う
AIを活用して作業効率が上がったことで、思いがけず新しい時間が生まれました。
その隙間時間を、商材の特徴やターゲット層を深く理解するためのリサーチに使うことが出来るようになったのです。
商材をしっかり知ることで、デザインの方向性やコピーの切り口もより的確に。
どんな見せ方が一番伝わるか、どんな言葉が響くか。
そんな部分に時間をかけられるようになったことで、デザインそのものの説得力が増したように感じています。
そして、“早く仕上げる”だけでなく、“より良く伝える”ための時間を増やせたことが、AI活用の一番の効果ではないかと感じています。
AIにできる部分はAIに任せながら、人にしかできない感性や判断を磨く。
これこそが、今の時代のAIと人が共に創造をする理想の形だと感じています。
まとめ
AIは、ただ便利なツールではなく、働き方や考え方そのものを見直すきっかけをくれる存在です。
テキストを打ち込むだけで、頭の中のモヤモヤまとまらないイメージをスッキリさせてくれるのも良いですね。
ただその一方で、生成物の扱いや著作権などに注意しながら、責任を持って使いこなす姿勢も欠かせません。
限られた時間の中でも、安心して、より良いデザインを届けられるように……。
デザインの最終的な判断は私の持つ「いいな」や「これは欲しくなるな」という感情を大切に制作したいので、AIを頼りつつも、頼りすぎず、これからも人とAIの“ちょうどいい共創”を探り続けていきたいと考えています。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました!